こんにちは。いろどりゆたかです。
今回は、「不要になった冷蔵庫をジモティで1,000円で売った話」から広がった、“不要品を求めている人に届ける方法”についてお話ししたいと思います。
「もう使わない=ゴミ」ではない
我が家には、約15年間使い続けた冷蔵庫がありました。
もともと1人暮らしをしていた頃に購入したもので、コンパクトで使い勝手のいいサイズ。ですが、子どもも小学校に上がり、食材の量も増え、さすがに容量が足りなくなってきました。
新しい冷蔵庫を家電量販店で品定めし、価格.comで比較して購入。送料・部屋までの搬入も無料で、納得のいく買い物ができました。
しかし、ここで出てくるのが「古い冷蔵庫、どうする?」という問題です。
引き取り料金は5,000円。でも…
一般的には、家電リサイクル法に基づいて引き取り料金がかかります。だいたい5,000円前後が相場。それを払って処分するのが常識かもしれません。
ですが、私は思いました。
「まだ使える。誰か必要としている人がいるかもしれない」
そこで思い出したのが、地域の掲示板「ジモティ」です。
「ダメもと」でジモティに出品してみた
すぐにスマホでジモティのアプリを開き、冷蔵庫の写真とサイズ、年数、動作状況などを正直に記載して投稿。「価格は1,000円。取りに来てくれる方限定」と書き添えました。
1週間ほど経ったある日、1通のメッセージが届きました。
「冷蔵庫、購入希望です」
話を聞いてみると、知人が一人暮らしを始めるにあたり、安くて小さめの冷蔵庫を探しているとのこと。まさにピッタリ。お互いに納得したうえで、引き取りの日程と場所を決めました。
初めての個人取引。だけど…
正直、最初はちょっと緊張もありました。
でも当日、指定場所で待っていると、連絡をくれた方が丁寧にあいさつをしてくれ、スムーズに受け渡しが完了。
冷蔵庫は彼の車に積まれ、私は1,000円を受け取りました。
それだけで終わり。とてもあっけないほどに、スムーズなやりとりでした。
「場所」が変われば、「価値」も変わる
この経験を通じて、私は一つのことを強く実感しました。
「モノの価値は、自分ではなく他人が決める」
自分にとっては不要でも、誰かにとっては必要なもの。
そして、そのモノが“再び誰かの暮らしで活かされる”ことほど、うれしいことはありません。
不用品を届ける5つのステップ
私が感じた「不要品を求めている人に届ける方法」を5つにまとめます。
① 捨てる前に「誰かの役に立てないか」を考える
不用品を捨てることは一番手軽で確実な方法ですが、その前に「これって、誰かが必要としていないだろうか?」と一度立ち止まって考えることが大切です。自分には不要でも、これから一人暮らしを始める人や、急に家電が壊れて困っている人にはありがたい存在かもしれません。ものの価値は持ち主が変わることで再び生まれ変わります。まずは譲る選択肢を持つ習慣が大切です。
② 価値の見直しと“伝える力”を磨く
見た目が古い、多少汚れているという理由だけで価値がないと決めつけるのはもったいないことです。たとえ年数が経っていても、「まだ使える」「簡単な掃除で十分きれいになる」「引っ越しや一時的な利用にちょうどいい」など、使う人にとってのメリットは必ずあります。その良さをどう伝えるかで、見向きもされなかった不用品が“必要とされるモノ”に生まれ変わるのです。
③ 信頼できるプラットフォームを活用する
不用品を誰かに届けるには、信頼できる“場”の選択が欠かせません。私が活用した「ジモティ」は、地域密着型の掲示板で、近隣の人と直接やりとりできる安心感があります。ほかにも、メルカリやラクマなどのフリマアプリ、LINEの地域グループなども有効です。さらに、自治体が主体となって「不用品掲示板」や「エコフリーマーケット」を開催しているケースも増えています。行政運営の仕組みは信頼性も高く、地域内で気軽に利用できます。また、リサイクルセンターに「譲ります/譲ってください」コーナーを設けている自治体もあります。こうした公的な仕組みも上手に活用すれば、安心かつスムーズに“誰かの役に立てる”一歩が踏み出せます。オフラインの場も有効に活用するとさらに届ける幅が広がります。
④ 情報は客観的に、誠実に
不用品を譲る際は、商品の状態を正確に伝えることが何よりも大切です。「キズあり」「10年使用」「動作に問題なし」など、良い点だけでなく不利な情報も包み隠さず書くことで、相手に安心感を与え、信頼につながります。誤解を招く曖昧な表現はトラブルの元。実物の写真を添えるとさらに信頼度が増します。大切なのは、“売る”よりも“誰かに託す”という誠実な気持ちを持って情報を届けることです。
⑤ “誰かのため”という視点を持つ
不用品を手放すとき、「少しでもお金にしたい」という気持ちもわかりますが、それ以上に大切なのは「誰かの暮らしに役立つかもしれない」という思いやりの視点です。この気持ちがあると、やりとりの対応も自然と丁寧になり、相手との信頼関係も築きやすくなります。譲った相手が喜んでくれる姿を想像するだけで、自分の心もかに。モノを通じて、人と人がつながる優しい循環を意識してみましょう。
出品時に気をつけたこと
- 写真は明るい場所で撮影する
→ 実物の状態がわかるように、自然光の下で全体と細部を撮影。 - 傷や汚れも正直に載せる
→ マイナス面も隠さず伝えることで、トラブルを防ぎ信頼感が生まれる。 - 説明文は客観的かつ丁寧に書く
→ 使用年数、サイズ、動作状況などを明確に記載。主観より事実を重視。 - 受け渡し場所は安全な人目のある場所に設定
→ 公共の駐車場や店舗前など、トラブル回避と安心感を意識。 - メッセージのやりとりは丁寧に・なるべく早く
→ 相手を不安にさせないよう、返信は早めに、丁寧な言葉づかいで。 - 時間や持ち物の確認など、事前準備をしっかり
→ 当日の待ち合わせに備えて、相手と詳細を共有しておく。 - 最後に「ありがとう」の気持ちを伝える
→ 「使っていただけてうれしいです」と感謝を伝えることで、温かな印象に。
まとめ:モノが“人の手”を渡って、再び生きる
長年我が家で働いてくれた冷蔵庫は、今、きっと新しい家庭でまた役割を果たしてくれているはずです。モノには“寿命”だけでなく、“居場所”もあるのかもしれません。たとえ自分には不要になっても、それが誰かの暮らしを支える存在に変わることがあります。
これは冷蔵庫に限らず、洋服や家具、おもちゃや本にも同じことが言えます。
「もういらない」ではなく「誰かに届けられないか」と考えること。
その一歩が、モノにとっても、人にとっても、そして自分自身にとっても、あたたかくてゆたかな循環を生み出します。
「いろどりゆたか」が大切にしているのは、日常のなかの小さなゆたかさ。
それは、物を大切にする気持ちだったり、誰かのためにできるちょっとした心遣いだったりします。
何気ない行動のなかに、想像以上のやさしさや、つながりが生まれることがある。
そんな「いろどり」と「ゆたかさ」が広がっていく社会であったらいいなと、心から思います。
ラッフィのひとこと
「もういらない、じゃなくて…誰かの“うれしい”になるかもしれないラフィ♪ ものにも第二の人生があるんだね!」

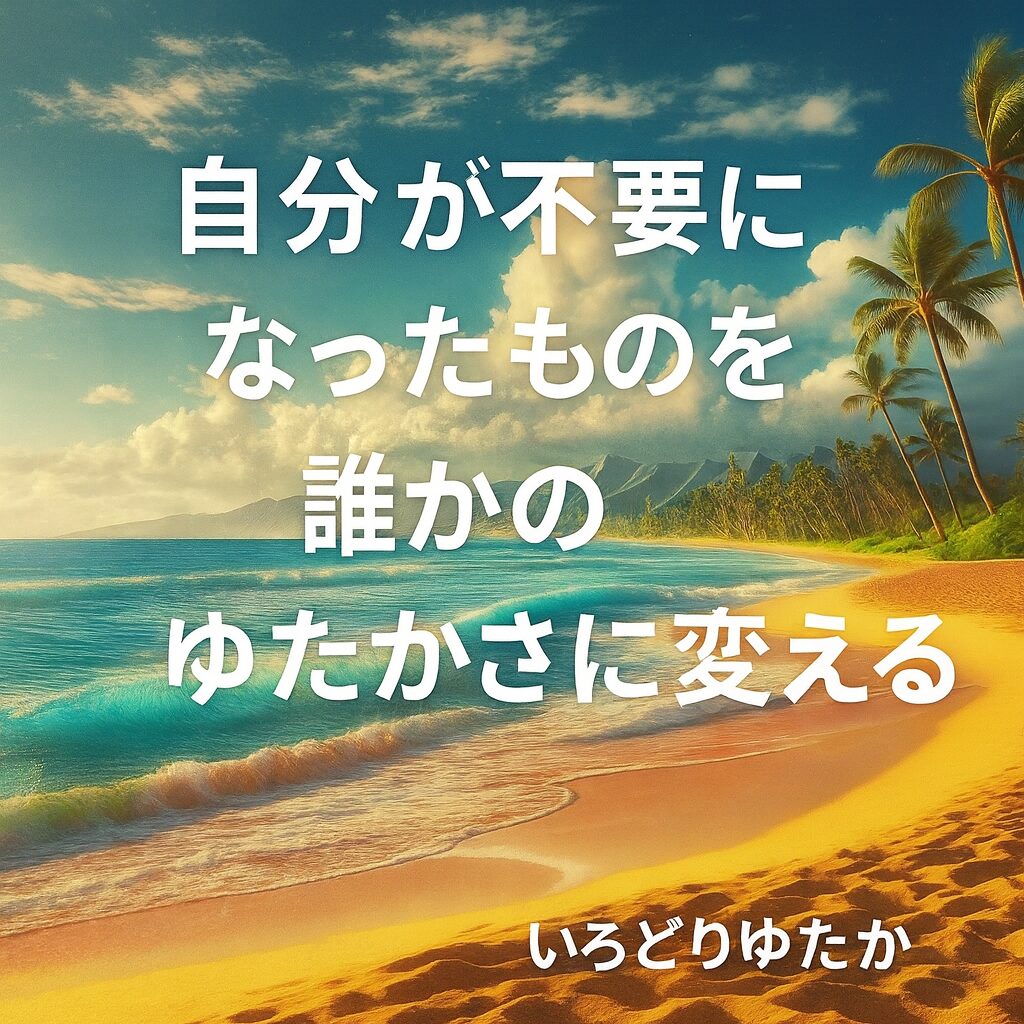



コメント