こんにちは。いろどりゆたかです。
これまで【パート1】と【パート2】では、「実際にあった境界線を超えてしまった体験談」、「境界線ってなに?」というテーマで、信頼関係における心の距離感や、人との間にある“見えないけれど大切な線”についてお伝えしてきました。
でも、ただ説明を聞いただけでは、子どもたちにとってはちょっとむずかしいこともありますよね。
そこで今回は、私が実際に小学校低学年の子どもたちに体験してもらった「遊びを通して楽しく・自然に境界線を体験できる方法」をご紹介します。
「これはイヤだった」「これなら安心できたよ」――
そんな気持ちに気づける体験を通して、心の距離感を育んでいきましょう。
信頼って、どうやって壊れるの?子どもたちに伝えたい「境界線」の話(パート1)
そもそも「境界線」って何?見えないけれど、とても大切な“心の距離”の話(パート2)
フラフープで「わたしの安心の輪」を感じてみよう!
目的
自分にとって「ちょうどいい距離感」「近づきすぎて嫌な距離感」を体験しながら、心の境界線(パーソナルスペース)を知ることができます。
準備するもの
- フラフープ(人数分 または 体験用1つ)
- 広めのスペース(教室やプレイルームなど)
手順
① 自分の輪をつくろう
参加者一人ひとりがフラフープの中に立ちます。
「これが“あなたの安心できる場所”です。ここはあなたのスペースです」と伝えましょう。
★ ポイント:このとき、フラフープに入った子に「今どんな気持ち?」と聞くと理解が深まります。
② 他の人が近づいてみる
もう一人の子が、ゆっくりとフラフープに近づいていきます。
「どこまで近づかれるとちょっとイヤな気持ちになる?」という感覚を、自分で感じてもらいます。
★ ポイント:近づかれる側の子が「もう少しOK」「ここはもうイヤ」とジェスチャーや言葉で伝えるように声掛けしていくと良いでしょう。
③ 感じたことを言葉にする
体験のあと、次のような質問をしてみてください。
- 「どこまで近づかれるとイヤだった?」
- 「どうしてイヤだったと思う?」
- 「安心できる距離ってどんな感じだった?」
★ポイント:ここで伝えたいことは、「安心できる距離感は人それぞれ違う」ということ。それを、みんなで共有することが大切です。
④ まとめ:「みんなが持っている“心の輪”を大事にしよう」
最後に、大人や先生がこう伝えてあげてください。
「今の体験で感じた“ここまでなら大丈夫”っていう距離は、心の中にもあるんだよ。
それが“境界線(バウンダリー)”っていうんだよ。
だから、人と関わるときには、その“見えない輪”を大切にすることが大事なんだね。」
① ぬいぐるみを使って「こうされたらどう思う?」を感じよう!
目的
子どもが「されたらうれしいこと」「イヤなこと」を感情と結びつけて理解し、他人の気持ちを想像する力を育てていきます。
準備するもの
- 子どもが好きなぬいぐるみ1体
- 安心して遊べるスペース
遊び方
- 子どもにぬいぐるみを選んでもらいます。
- 大人がぬいぐるみ役になり、いろいろな行動をして見せます。
- ぎゅっとだっこする
- かってにカバンを開ける
- やさしく話しかける
- 子どもに「ぬいぐるみはどう思ったと思う?」と聞いてみましょう。
- 今度は子どもがぬいぐるみ役、大人が相手役になり、立場を交代してもう一度行います。
声かけの工夫
大人側の行動に対してどう感じたかをその場ですぐに子ども自身が伝えることが大切です。「今どう思った」「今の気持ちを言葉にしてみようか」と声掛けしてみてください。でも、低学年生だと、まだまだ自分の気持ちを表現することが難しいので、子どもが伝えたい言葉のヒントを大人側が出してあげると表現しやすいかと思います。
ポイント
気持ちには「いい・わるい」はなく、感じ方は人それぞれ違うことを伝えましょう。「これってイヤだったかも」「これはうれしかった!」という発見を大事にします。
② 絵カードを使って「これはいい?それともイヤ?」の気持ちを当てよう!
目的
他人の気持ちを想像し、「してもいいこと」と「してはいけないこと」の区別を感情の視点から理解する力を育てます。
準備するもの
- 場面イラストの絵カード(例:友達と遊ぶ、カバンを勝手に開ける、助けてもらうなど)
このカードを作るところから始めても良いと思います。
遊び方
- 絵カードを1枚ずつ見せて、「このときどう思う?」と質問します。
- 子どもが「うれしい」「イヤだ」「こわい」など感じたことを答えます。
- 答えに正解はなく、「なんでそう思ったの?」と理由を聞くことで対話を深めます。
例題(カードの内容)
- 友達がかってにランドセルをあけた →「どう思う?」
- やさしく声をかけてもらった →「どんな気持ちになった?」
- しつこくさわられた →「うれしかった?イヤだった?」
ポイント
「気持ちを考えること=相手を思いやること」だと自然に学べる構成にしましょう。日常の場面とつなげながら「これも境界線だね」と結びつけていくとより効果的です。
■ おわりに
今回は、私が実際に小学校低学年の子どもたちに体験してもらった「遊びを通して楽しく・自然に境界線を体験できる方法」について紹介しました。
遊びながら境界線を体験することで、子どもたちは「自分の気持ち」「相手の気持ち」に気づきやすくなります。また、「それってちょっとイヤだったな」「それなら安心できるよ」と言える力を育てていけると、自分を守る力も身についていくことでしょう。
境界線は心を守るやさしい線。遊びを通して、子どもたちの“安心の輪”を育てていきましょう。
■ 参考・引用文献
- ConnectABILITY.ca(2021)
Teaching Personal Space to Children Using Games and Activities - Random Acts of Kindness Foundation
How Big is Your Hula Hoop? – Social Emotional Learning Resources - Socially Skilled Kids(2022)
Teaching Personal Space: Activities and Strategies - 日本発達支援センター『パーソナルスペースを学ぼう』(2020年)
※子どもの社会的スキル支援教材(非公開資料を一部参考)
※当記事は、上記資料をもとに小学校低学年向けにわかりやすく再構成した実践記事です。
ラッフィのひとこと
「ぼくにも “ここから先はちょっとイヤかも” っていう心の輪があるんだ。みんなにもきっとあるよね」




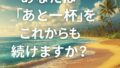
コメント