はじめに
こんにちは。いろどりゆたかです。
今回は、私が地域のサッカークラブでコーチとして活動する中で感じた「気づき」や「学び」についてお話ししたいと思います。
実は私は、普段は児童福祉の仕事に携わっています。
日々、子どもたちと関わる仕事をしているので、「サッカークラブでも同じように接すればうまくいくだろう」と、最初は少し安易に考えていました。
でも実際は、思っていたよりもずっと“違い”がありました。
立場の違い、環境の違い、そして「ここに来る目的」の違い。
仕事で関わる子どもたちは“生活の中”で支援が必要な子が多い一方、サッカークラブに来る子どもたちは“サッカーを楽しみたい”という明確な目的を持っています。
最初は戸惑うこともありましたが、その違いに気づいたと同時に「共通点」もたくさん見つけることができました。
子どもたちの心の動きや成長のプロセスは、どんな環境でも変わらないのです。
これまでの経験や知識を生かしながら、サッカーを通じて子どもたちと向き合い、“いろどりコーチ”としてのスタイルを少しずつ築いていきたいと思っています。
では、「いろどりコーチのサッカージャーナル」――スタートです!
「楽しむ」がすべての原点
少年サッカーを指導していて、私がいちばん大切にしている言葉は「サッカーを楽しもう」です。
勝つことは素晴らしい。しかし“楽しさ”を犠牲にしてまで勝利だけを追い求めるのは、育成年代では本質を外します。
プロの世界では勝利のために徹底することがある――私が応援している鹿島アントラーズは、後半アディショナルタイムにコーナーフラッグ付近でキープして試合を締めることがあります。あれは“チームの約束”であり、サポーターに勝利を届ける“勝つための美学”。だからこそ強い。ただ、それをそのまま地域ジュニアクラブに持ち込むのは違う。
サッカーを始めたばかりの子どもたちは、まず“経験”で知っていきます。ボールを転がす、蹴る、ゴールに入る、ドリブルで相手を抜く――その“できた!”の積み重ねが楽しさを育てる。ここに「外へ蹴れ!」「キープしろ!」だけを強いてしまうと、サッカーを好きになる入口を狭めてしまいます。
だから最優先事項は、ボールを追う・蹴る・決める喜びを味わわせること。“楽しい”がすべての原点です。
試合前のひとことは「楽しんでこい」
ある大会で、私は選手たちに「今日は楽しんでこい!」とだけ伝えてピッチへ送り出しました。相手は格上。結果は惜敗でしたが、戻ってきた子どもたちの顔は晴れやかでした。
私は試合中は“勝つための声かけ”をします。けれど、送り出すときは“楽しむための声かけ”をする。この“温度差”が子どもの心に余白をつくり、伸び伸びとしたプレーを引き出します。結果に縛られず、心から楽しんだ体験は、次の挑戦の燃料になります。
「二つの人種」が生まれる時期
小学校中学年(U10)ごろになると、チームには大きく二つのタイプが現れます。
- ① 県大会に行きたいほど勝利志向が強い選手
- ② サッカーの楽しさを知っている途中の選手
指導者としてどちらに寄せるべきか悩む場面は多い。私は「サッカーを楽しもう」という軸をぶらさないと決めています。
楽しさという土台があるから、自然に“もっと上手くなりたい”“勝ちたい”が芽生える。逆に楽しさを奪われた途端、子どもはボールから離れていく。
勝ちたい子も、今は楽しみたい子も、共通して必要なのは「このチームでサッカーをするのが好きだ」という気持ちです。そこを育てるのが最初の仕事です。
U10世代に伝えたいこと
“できる”より“考える”を育てる
この年代で大切にしているのは、技術よりも「サッカーを知ること」。私は練習でしばしば5W1Hを使います。
- いつ やる?いつから攻める/守る?いつやめる?いつ始める?
- どこ でやる?どこで蹴る?どこへ走る?どこに向かう?どこがゴール?どこを守る?
- 誰 と試合する?誰がいる?誰の指示に従う?誰のために?誰が喜ぶ?誰のおかげ?
- 何 を蹴る?何を見る?何を知る?
- なぜ パス?なぜシュート?なぜ守る?なぜヘディング?
- どのように 走る?蹴る?守る?攻める?
正解を教えるのではなく“考えるきっかけ”を渡す。この積み重ねが“サッカーを理解する力”になります。
ある練習で、ミスして落ち込む選手に「今のプレー、どうしてそうした?」と聞いたところ、「ゴールを見たらシュートしたくなった」と返ってきた。私は「最高の気持ちだよ」と即答しました。気持ちに寄り添いながら“なぜ”を一緒に辿る。これがコーチングだと感じます。
「教える」よりも「寄り添う」
かつて私はコーチングを「教えること」だと思っていました。今は明確に違うと感じています。
“教える”はティーチング。“寄り添う”がコーチング――この言葉が私にはしっくりきます。知識を伝えるだけでは足りない。心の動きに気づき、次の一歩を一緒に探す存在でありたい。
試合中、失点の原因になって泣き出した選手に私は「お前のせいじゃない」と慰めず、「次、どうすれば守れたと思う?」と静かに尋ねました。少し間があってから「前の仲間に声をかければよかった」と彼。あの瞬間に“反省”ではなく“気づき”が生まれた。叱責では育たない自立が、問いかけから芽吹くことを現場で学びました。
『コーチングとは信じること』から学んだ5つの力
コーチを始める頃に出会った一冊――ジョン・ウィットモア『コーチングとは信じること』。この本は“寄り添うコーチング”の教科書でした。特に共感したのは次の5つです。
① 信じる力
選手を“できる存在”として信じると、言葉が変わる。「なんでやらない?」「なぜできない?」ではなく「どうしたらできる?」へ。期待しているからこそ、まずはその場で選んだプレーを認め、次の可能性へアプローチする。これが行動のエンジンになります。
② 問いかける力
答えを先回りして与えず、考える余白をつくる。「次はどうしたい?」の一言で主体性は動き出す。経験の少ない子どもは“先”を想像しにくい。だからこそ“やらせてみてから問う”。必要に応じてヒントで導く――これも有効な手法です。
③ 傾聴する力
うなずき、最後まで聴く。子どもは「間違っているかも」という不安で口を閉ざしがちですが、聴いてもらえるだけで安心が生まれ、挑戦の意欲が戻ります。経験豊富な大人こそ、結論を急がず耳を傾けたい。
④ 目標を共有する力
“与える目標”ではなく“引き出す目標”。自分で決めた目標は、自分で追いかけたくなる。目標が漠然としている場合は、短期のミニ目標まで具体化し、選手の現在地へ落とし込む伴走が大切です。
⑤ 信頼関係を築く力
結果よりプロセスを見守る姿勢が、子どもの心を開く。小学生はサッカー人生の“終わり”ではない。負けや失敗の免疫をここでつくっておけば、その先で何度でも立て直せる。失敗を次に繋げる橋を架けるのがコーチの役割であり、その土台が“信頼”。言葉に力が宿るのは、関係が先にあるときです。
これらはすべて「寄り添うコーチング」へと収束します。指導とは、子どもの内にある可能性を信じ、光を見つける旅だと感じます。
『JFAキッズガイドライン』で共感した5つの指導観
ライセンス取得時の講義とガイドブック――『JFAキッズガイドライン』は、現場の私に最も大きな影響を与えた一つです。
子どもたちをささえる大人のみなさまへ『JFAキッズガイドライン』
① 楽しむことがすべての原点
“うまくなる”より“好きになる”を最優先に。私はもともとこの考えで取り組んできましたが、ガイドラインで裏づけを得て、ポリシーとして確信に変わりました。
② 発達段階に応じた指導
U8・U10・U12で求めることは異なる。成長スピードも個々に違う。科学・心理の知見に基づけば、無理な要求や年齢不相応の指示を避けられる。感覚プレーから“考えるプレー”へフェーズを移すきっかけを意図的に設計できるのも利点です。
③ 失敗を恐れず挑戦させる環境
私は“失敗の数=学びの数”だと伝えています。安心して失敗できる場をつくるために、叱責ではなくリフレクション(振り返り)の時間を確保する。「なぜその選択をした?」「他の選択肢は?」――問いと対話で挑戦の回数を増やします。
④ 自立を促す声かけ
先回りして答えを言いたくなる衝動をいったん飲み込み、子どもが自分で判断・行動できるよう導く。これはプレー外の生活でも同じ。宿題・翌日の準備など、親や大人が“奪いがち”な機会を返すことが自立の土台になります。
⑤ 仲間との関わりを重視する
サッカーはチームスポーツ。相手・審判・保護者・仲間へのリスペクト、頼り頼られる関係、感謝の実践。技術以上に価値のある成長がここにある。勝敗に関わらず、ここを育てたチームは長期的に強くなります。
これらは「人を育てるサッカー」を目指す理念そのもの。指導者である私自身も、子どもたちと“楽しみながら学び合う”姿勢を忘れないようにしています。
実例:声かけの「置き換えリスト」
- 「なんでできない?」→「どうしたらできる?」
- 「今はダメ!」→「次はこうしてみよう」
- 「失敗するな」→「試す価値はある。試してから振り返ろう」
- 「早く決めろ」→「君はどうしたい?その理由は?」
- 「言われた通りに」→「自分のアイデアを足すとしたら?」
小さな言い換えが、子どもの主体性を守り、関係の質を上げます。
コーチとしての理想像――“同じ方向を見て伴走する”
育成年代で最重要なのは、テクニック以前の「関係づくり」。上から指示する“支配者”ではなく、横に並んで一緒に歩く“伴走者”でありたい。
子どもが笑顔でボールを追う姿を見て、私たち指導者もまた“サッカーの原点”を思い出す。「サッカーを楽しむ」という言葉は、子どもだけでなくコーチ自身へのリマインダーでもあるのです。
まとめ――信じて、問い、聴き、共に歩む
- 原点は「楽しむ」
- 送り出す言葉は「楽しんでこい」
- U10では“できる”より“考える”
- ティーチングよりコーチング、“教える”より“寄り添う”
- 信じる・問いかける・傾聴・目標の共有・信頼関係――この5つを日々実践する
コーチングとは、子どもを信じ、寄り添い、共に歩むこと。
その過程に、勝敗以上の“ゆたかさ”がある――私はそう信じています。
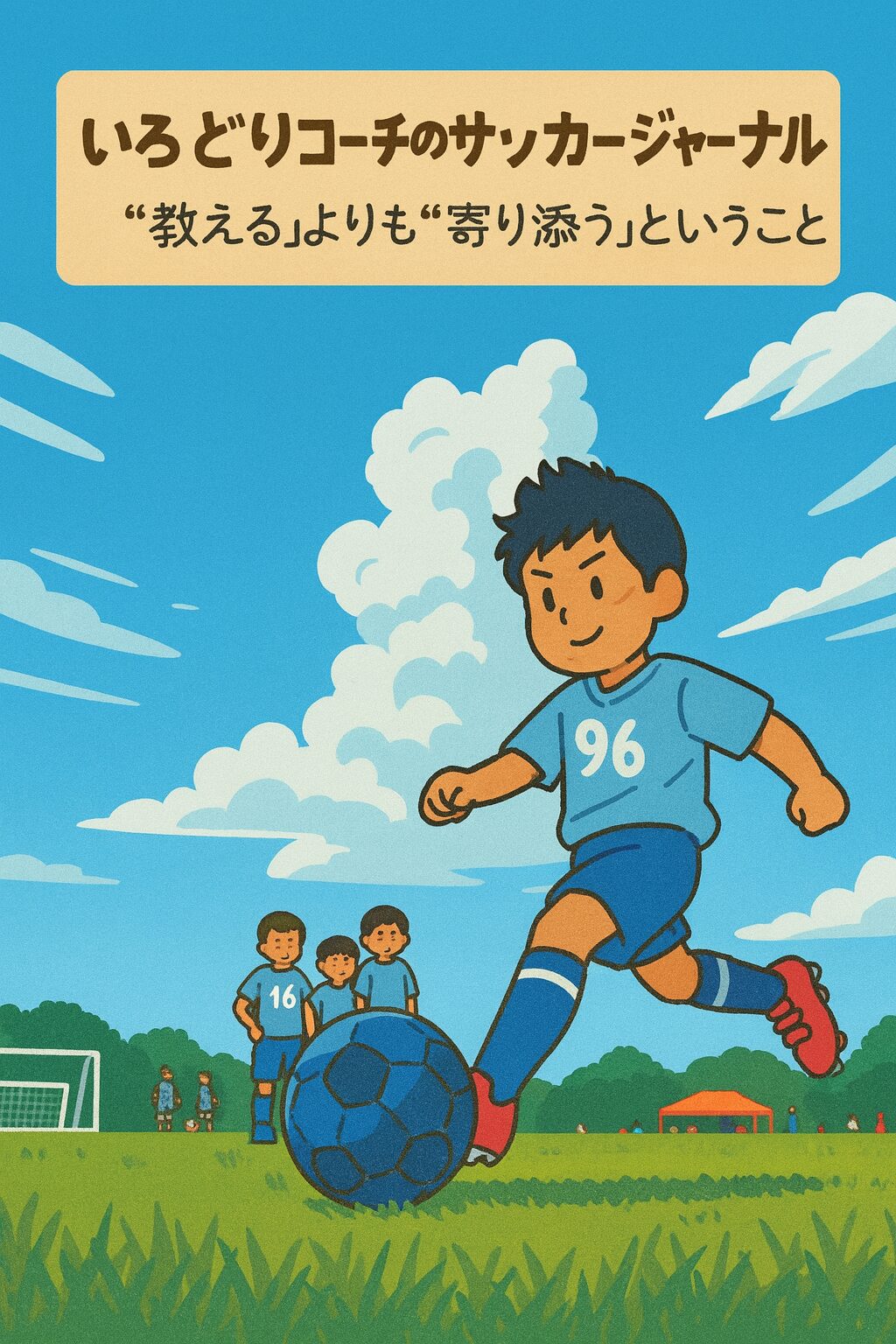

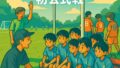
コメント