こんにちは。いろどりゆたかです。
先日は中秋の名月。いろどり家では赤飯と豚汁をいただきます。
ずっと“赤飯が主役で、豚汁は脇役”だと思っていました。
けれど今日ふと気づいたんです。赤飯のあとに、あたたかい豚汁をひと口すすると——
「主役はお前だったのか!」って。
脇で支えていたと思っていた存在が、実は全体を引き立てていた。
そんな小さな気づきに、秋の“ゆたかさ”を感じました。
さて、今回は、いろどりコーチとして初めて公式戦を指揮した時の話。
低学年(U10)チームを任されたいろどりコーチが、試行錯誤と迷いの中で得た学びをまとめます。
同じ悩みを抱える方に届けば嬉しいです。
それでは、いろどりコーチのサッカージャーナル、スタートです!
U10のヘッドコーチ就任──不安と決意
小学校4年生主体のU10世代の公式戦。私がヘッドコーチを任されました。
まだ力量も器も定かでない中、正直に言えば不安だらけ。
この年代で「どこまで求めるのか?」——勝利は大切。でも“楽しさ”がないサッカーを子どもたちは求めていないはず。幼稚園から続けている子もいれば、最近はじめた子もいる。何を基準に練習を設計すべきか定まらない。
しかも自分の息子もいる、いわゆる“パパコーチ”。やりづらさもある。
——それでも、悩んでいても始まらない。いま出来ることをやる。 そう決めました。
予期せぬ出発点──守護神の“旅立ち”
4月に始動したチームに早速の転機。
一緒にやってきたGKが有名Jクラブのセレクションに合格。6月から移籍することに。
残念さはあるけれど、それ以上に嬉しい。その子にとってのステップアップだから。盛大に送り出しました!
GK不在問題と“挙手”の勇気
次のGKは誰に? 当然みんなやりたがらない。前任者が上手すぎたから。
そんな中、「僕やります!」と手を挙げた子がいました。
後でお母さんから「家では泣きながら“本当はやりたくない”と言っていた」と聞きました。
10歳の子に“やりたくないGK”を任せるべきか、かなり悩みました。
でも、その挙手の勇気を無駄にしたくない。GK練習をしっかりやって移籍したGKに負けないくらい上手な選手にしてあげると心を決めました。
チームに伝えた“2つの約束”
サッカーだけでなくこれから成長していく上で大切になってくることをまずは伝えました。
- たくさんチャレンジして、たくさん失敗すること
- やらない言い訳を考えないこと
この2つを、まずは“メンタル面の約束”として徹底しました。
技術・戦術の“共通言語”づくり
最初から技術を多くは求めないつもりでしたが、最低限の共通言語は持たせました。
ディフェンス(基本)
- 相手にボールが入っていないうちは“誰のボールでもない” → 奪いに行く
- 相手がボールを受けたら → 前を向かせない
- 相手が前を向いたら → 飛び込まない
コートを3分割した考え方
- ディフェンシブサード(自陣ゴールに近い“絶対に失ってはいけない”ゾーン)無理なドリブルは避け、確実にパス。
- ミドルサード (攻撃準備のエリア)パススピードを上げるスイッチを意識。
- アタッキングサード (仕掛ける・シュートをまず狙う)ここで奪えば得点確率が高い。
攻守の原則
- 守備はコンパクトに、攻撃はワイドに
- 攻撃したら走って戻る(トランジションの徹底)
これらを試合でイメージできる全体像として共有。
“伝えたこと”だけを評価する。伝えていないことを叱らない。
共通テーマがあるほど評価基準は明確になり、褒める機会も増えます。
小学生年代は“感覚と刺激”で吸収する時期。でも、戦術のフックを作っておくと、確実に視野が広がる。
鏡としての選手たち──言葉の修正
練習試合を重ね、できることが増えていく手応え。
しかし上手い相手との試合では守備時間が長く、試合が“つまらない”と感じ始める子も。
「なんでそっちに蹴るの?」「なんで行かないの?」——選手同士の文句が増え、雰囲気が悪化。
その言葉、どこかで聞いたことがある。
……私が言っていた。
選手はコーチの鏡。子育ても同じ。
反省しました。 私の言葉の影響で子どもたちを苦しめていたのかもしれない。
以後、責任ある行動・毅然とした態度・前向きな姿勢を自ら体現することを誓い、
選手に謝罪。考え方をリセットして再スタートを切りました。
思わぬアクシデント──主力の負傷
公式戦1か月前。遠征や地域大会で過密日程の中、主力選手が接触で負傷。
診断は足首の剥離骨折・全治3か月。貴重なサイドバックで代替が効かない痛手。
次の練習で本人は「サポーターすれば大丈夫。出られます」と訴える。
私は「君は試合には出さない」と伝えました。
この公式戦が最後ではない。将来有望だからこそ“今”を大切に。
足首は癖になりやすい。目先より長期を見よう。
彼は泣いていましたが、それでも練習・試合に帯同し続け、チームの一員として行動し続けました。
この年齢でその姿勢、本当に立派です。
フォーメーションの試行錯誤
布陣は迷いに迷いました。守備的にするか、2バックで攻撃的に賭けるか、3-2-2か。
最終的には3-3-1というベーシックに立ち返り、原則の徹底で臨むことに。
公式戦当日
大会当日。会場に選手が集まってきました。緊張して顔がこわばっている子、まだ寝ぼけている子。
キックオフまで1時間。
いつものルーティンで安心感をつくる
選手の緊張を和らげるために、そして、体と頭を覚醒させるために毎回の試合や大会のウォーミングアップでやってきたことを今日もやります。試合の前にやることはなるべくルーティン化して選手たちの安心と自信に繋げるためです。
・フィジカルトレーニングで体をぶつけ合う。→ 振動と衝撃を体に与えていくことで体が起きてくる
・パスワークでボールと足の感覚を慣らす。→ 今日の足の感覚や芝の状態などを確かめていく
・ウォーミングアップ中のポジティブな声かけを選手に共有。 → 前向きな言葉がけで気持ちを整理していく
「失敗を恐れるな」「たくさん失敗していい」「言い訳を考えるな」 いつもの言葉を繰り返し、ピッチへ。
第1試合:強豪相手に0-3の前半
第1試合:強豪相手に0–3の前半
相手は前評判どおりの強豪。
地区リーグ無敗のチームという情報だけで、子どもたちの表情には緊張が走ります。
それでも私は伝えました。
「何が起きるかわからないよ。」「サッカーの女神は細部に宿る。」と。
試合開始のホイッスルが鳴り、ゲームが流れます。
選手たちのプレーはやはり硬く、本来の力を出せない。どこか“人任せ”なプレーが続きました。
前半3分。右サイドを崩され、アーリークロスがゴール前へ。
ディフェンスとキーパーの間に入ったボールに対し、サイドバックはキーパーに任せ、キーパーはサイドバックに任せてしまう——わずかな譲り合いの隙を突かれ、後方から走り込んだ相手がシュート。
痛恨の先制点を許してしまいました。
項垂れる選手たち。
その後も立て直せず、立て続けに2失点。前半終了時点でスコアは0–3。
ベンチに戻る子どもたちの足取りは重く、中には涙をこぼす選手もいました(それが、我が家の長男くんでした)。
「泣いてんじゃねー」「まだ終わっていないだろう」と声を荒げたい気持ちを抑え、
私は心の中で言い聞かせました。今やるべきは叱咤ではなく、マインドの再起動。
「プレーに失敗はつきもの。自信を持って失敗してこい。」
「まだ後半がある。巻き返そう。」
言葉を尽くしましたが、どんな声がけが選手の目の色を変えるのか、正直わかりません。
それでも、励まし続けることだけはやめませんでした。
選手たちの背中を押し、後半へと送り出しました。
後半:1点を返すも1-4
後半も押し込まれる時間が続き、なかなかボールを相手陣へ運べません。
それでも諦めずに守り続ける中、キーパーのロングキックが相手ディフェンダーの頭上を越え、ゴール前へ転がります。
そのボールを追っていたフォワードが反応。勢いのないシュートながらも、キーパーがキャッチミス。
ボールはゆっくりとゴールラインを越えました。
「よっしゃー!」「やった!」
ベンチもスタンドも歓喜に包まれる。待望の1点、貴重な1点でした。
ゴールを決めた選手は嬉しさのあまり、保護者席の前まで走っていってパフォーマンス!
しかし、私はツッコミます。
「違う違う! 負けてるんだから早くボールを持ってきて再開して!」
……もちろん、夢中で聞こえていません。
そもそも、なぜすぐ再開が大事なのかという仕組みを、私が十分に伝えきれていなかったんです。
グループリーグでは勝点・得失点差・得点数で順位が決まります。
つまり、1点でも多く取り返すことが大切。
そこを事前に説明しておくべきでした。これも私の経験不足からの反省点です。
1点を返して勢いづいたように見えたチームでしたが、引水タイム後、再び失点。
これでスコアは1–4。万事休す。
試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、崩れ落ちる選手、泣き出す選手。
それぞれが何かを感じ、胸に刻んだ表情をしていました。
ただ、トーナメントではない。これで終わりではない。
本来ならそこも試合前にしっかり共有しておくべきでした。
ベンチに戻ってきた選手を労う間もなく、次の試合への切り替えを促します。
「これで終わりじゃない。次がある。もう一度立て直そう。」
しかし、気持ちの切り替えは簡単ではありません。
子どもたちにとって、こうした経験はまだ数えるほど。
それも当然のことです。
そこで私は、“気持ちを立て直す方法”と“次への準備”*について丁寧に話しました。
軽い捕食を取りながら、先ほどの試合を一緒に振り返り、反省点を共有。
30分後の第2試合へ向けて、再び心と体のスイッチを入れ直しました。
第2試合目:意識が変わった30分
30分後、いろどりチームの2試合目が始まりました。
気持ちを切り替えてピッチへ向かう選手たちの顔には、先ほどまでの涙はもうありません。
前の試合で感じた悔しさが、エネルギーに変わっていました。
試合開始のホイッスルと同時に、全力でボールを奪いにいく。
1試合目とは明らかに違う立ち上がり。全員が「やってやる」という気迫に満ちています。
前半5分、相手のクリアミスを奪ってドリブル突破。
そのままシュート——先制!
ベンチからも歓声が上がります。
ゴールを決めた選手はすぐにボールを拾ってセンターサークルへ。
「すぐ再開だ!」
1試合目との違いがはっきり見えました。きちんと伝わっている。
続く9分、右サイドからトップの選手へスルーパス。
冷静に流し込み、追加点!
前半終了時点でスコアは2–0。
しかし選手はまだ満足していません。
「先ほどの試合で失った3点を取り返すぞ」「いや、それ以上だ」
そんな思いがチーム全体に漂っていました。
後半開始早々、ディフェンダーのクリアミスを拾われて1失点。
思わず「やってしまった…」と口をつきましたが、すぐに気持ちを切り替えます。
すると、ピッチから声が。
「切り替えよう!」「まだいける!」
この言葉を聞いた瞬間、胸が熱くなりました。
この短時間で、確実にチームの意識が変わっている。
ベンチから見ていて、成長を感じた一瞬でした。
そこから相手チームの怒涛の攻撃が続きますが、全員で体を張って守り抜く。
キーパーがキャッチして前線へロングキック。
ボールは相手ディフェンダーの頭上を越え、走り込んだ選手が全速力で追う。
数的優位を作り、最後はキーパーをかわして3点目のゴール!
相手は1試合目よりもややレベルが低いチームでしたが、
それ以上にこちらのチームの“気迫で勝った”試合でした。
その後も何本か得点チャンスはありましたが、追加点はならず試合終了。
結果は3–1で勝利。
ベンチに戻ってくる選手たちとハイタッチを交わし、全力を出し切った姿を讃えます。
誰一人として手を抜く者はいませんでした。
試合後のストレッチ中、子どもたちの口から自然と振り返りの言葉が出てきます。
「あそこ、パスもうちょっと早ければ通ったね。」
「戻り遅かったかも。」
負け試合のあとには見られなかった“内省の対話”。
この短時間でここまで変わるとは思っていませんでした。
勝利よりも嬉しかったのは、この“意識の変化”。
それが、何よりもこの日の最大の収穫でした。
結果:県大会出場ならず
初戦の相手が5-0で圧勝。我々は県大会出場ならず。
残念だけれど、これがいまの実力。それを受け入れるところから再出発です。
初公式戦を指揮して感じた“学び”
- グループリーグの戦い方を事前に“選手にも”理解させる(勝点/得失点差/得点の意味)。
- 小学年代でも、出る以上は大会のルールと戦略を共有する。
- 全員が“自分が主人公”の当事者意識でプレーする。相手任せにしない。
- コーチの言葉はチームに反射する。批判が増えたら、自分の声かけを疑う。
思い返せば反省は尽きません。でも一つ確かなのは、この敗戦を次につなげるのが私の仕事だということ。
叱咤か賞賛か——何がこの子たちに腹落ちするかを探り続け、言葉と環境で背中を押す。
コーチに求められることは計り知れません。けれど、子どもたちの未来に携わる役目であることは間違いない。
私自身も、この経験をここで終わらせず、学びと実践を積み上げていきます。
終わりに──子どもたちとともに成長するコーチでありたい
今後も「いろどりコーチのサッカージャーナル」として更新を続けていきます。
指導方法、関わり方に迷った時、悩んだ時こそ、子どもたちの輪の中に入って、同じ空気に触れること。
それこそが、指導者であり、養育者としての根っこの部分だと思っています。
私自身もまた彼らと同じ“主役”の一人として、
日々の練習や試合を通して成長を続けていきたいと思います。
ラッフィのひとこと
「子ども達の輪の中にこそ、コーチの答えがあるんだね。」
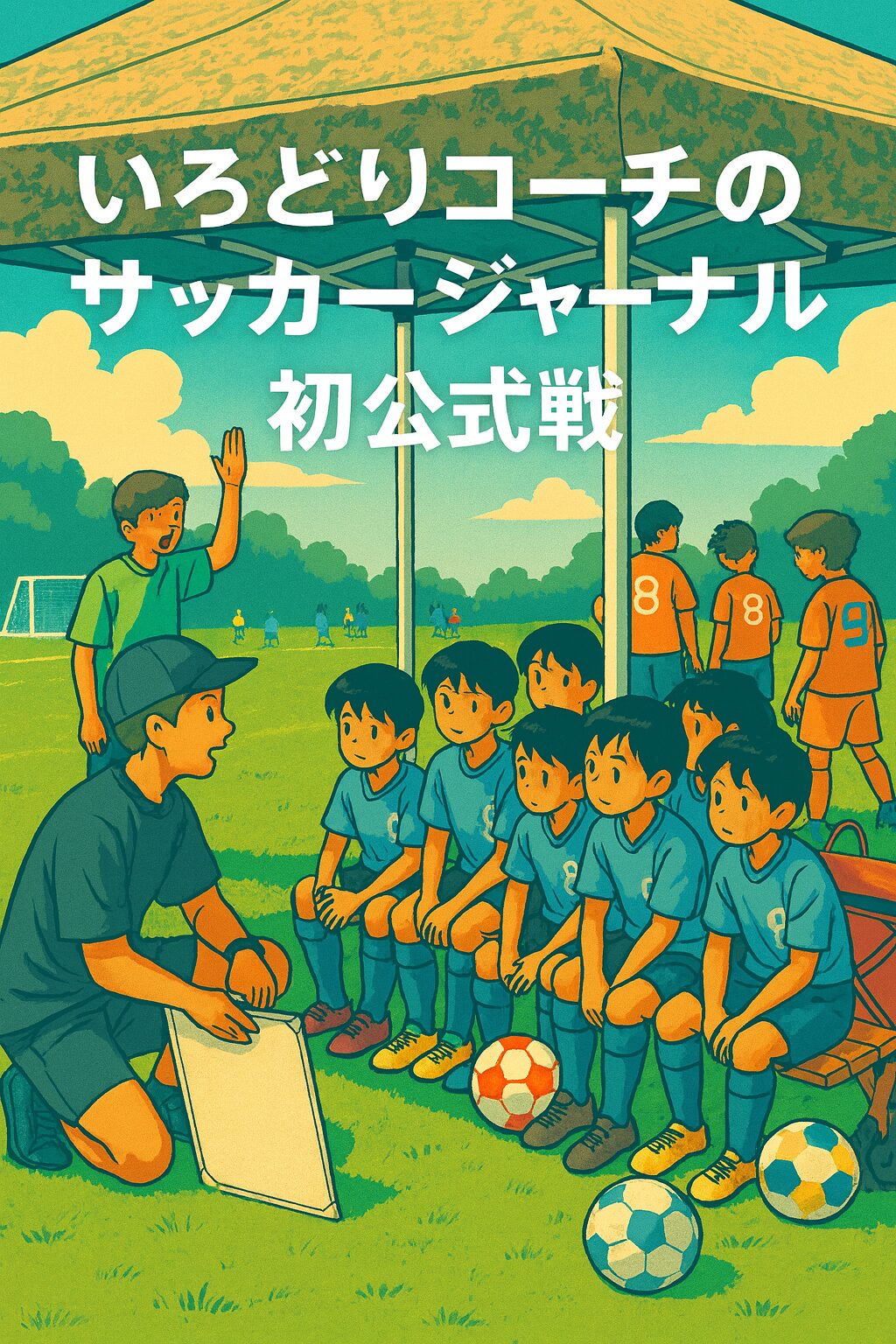


コメント