こんにちは。いろどりゆたかです。
暑い暑い夏も過ぎて、朝晩は過ごしやすくなってきました。外では稲刈りが進んでおります。
そんな中、私の最近の悩みは――稲刈り後の野焼きと花粉。田舎では避けられないこの時期の天敵です。
洗濯物は臭くなるし、くしゃみは止まらない…。ここに住む以上、共存していくしかありません。
さて、今回のブログテーマは「少年サッカーコーチとしての日々の出来事や学び」について。
春から地元少年サッカークラブのコーチを本格的に始めた私が、「コーチングって何?」という視点も含めて綴っていきたいと思います。
コーチという立場、そして「パパコーチ」
「教える」というより、子どもたちと一緒にサッカーを楽しみ、成長していく立場。
コーチとはどういう立場なのか、考えさせられる毎日です。
さらに、私の息子もそのクラブに所属しているので、いわば「パパコーチ」。
この立ち位置もまた難しいものがあります。
このブログでは、
- 練習や試合での気づき
- 子どもたちへの声かけの工夫
- 息子への関わり方
- そして自分自身の成長
これらを記録していきます。
サッカーを通じて「人との関わり」「学び方」「物事の考え方」「チームワーク」をどう伝えられるか読んでくださる方にも何かヒントになればうれしいです。
コーチを始めたきっかけ
私がコーチをするのは、長男くんが所属する地元の小さなクラブ。
もともとは小学校単位の少年団として活動していましたが、少子化で人数が減り、隣の小学校と合併してクラブチームとして活動を続けています。
私は当初、ただの保護者。練習やイベントの送迎をする程度でした。
実は私自身、このクラブの前身である少年団でサッカーを始め、小学2年から夢中でボールを蹴ってきました。家の庭でボールを蹴っては、引き戸のガラスを割って母に怒られたこともしばしば(笑)。
父と私の思い出

父は野球好きで、私に野球をやらせたかったようです。遊ぶときはキャッチボールばかり。
正直つまらなくて、すぐにドリブルやシュートを始める私…。
それでも父は、暗くなるまで私の前に立ち、ディフェンス役をしてくれました。
さらに夏になると、父は地区子ども会のソフトボールチームのコーチも担当。
私は「サッカーやりたいのに、自分の父親がコーチなんて…」と嫌でたまりませんでした。
それでも最後まで続け、町の大会で優勝するほど強いチームに育ちました。結果的に野球も得意になったのです。
この経験から私は思います。
「親がコーチだと、子どもは嫌なんだよなあ」
おそらく長男くんも、同じ気持ちを抱いているのではないでしょうか。
指導者不足の現状
サッカー指導者の登録数自体は、JFAの統計によると2000年代以降増加傾向にあり、2021年度から2022年度にかけても増加が見られます。しかし現場の肌感覚とは必ずしも一致しません。特に地域の少年クラブでは「指導者不足」が深刻で、毎回違うコーチが練習を担当したり、コーチが1人しかいないため1年生から4年生まで同じメニューを繰り返すといった状況が見られます。私自身もそうした環境に直面して「大変だな」と感じました。
ところが不思議な巡り合わせで、昔からサッカーを共にしてきた仲間や先輩が、偶然にも長男と同世代の子どもの保護者として集まったのです。
親友や憧れの先輩、社会人チームで共にボールを追った友人――気づけば自然とサッカー経験者が揃い、指導体制を支える力となりました。
数字上は増えていても、地域や現場レベルでは指導者の偏在や不足があり、結局は「誰がその場に立ってくれるか」が子どもたちの環境を左右するのだと実感しています。、
代表からのひとこと
ある日、クラブ代表から声をかけられました。
「一緒にコーチやらないか?」
答えは即「ノー」。
仕事や子育てに追われ、自分の時間もほしい。毎週練習、試合の日は丸一日…。とても無理だと思いました。
しかし代表は食い下がります。
「練習だけでもいい」「知識や経験を子どもたちに伝えてほしい」
確かに長男を練習や試合に送迎するなら、どうせ現場にはいる。
「仕方ないか…」と、渋々承諾しました。
やる気0%、やらされ感100%――これが、私がコーチを始めた最初のモチベーションです(笑)。
【スポーツをする子どもにこそ必要な栄養】アミノ酸が体に与える力とは?
これからどうなる!?
果たして、やる気0%で始めた「いろどりコーチ」。
どこでモチベーションが高まり、どんなやりがいを見つけていくのか。
次回は――そのいろどりコーチが練習に参加して感じたことについて、まとめていきたいと思います。
ラッフィの一言
「いろどりさんがこれからどんな指導者になっていくのか楽しみだな」

【いろどりコーチのサッカー日誌 vol2】サッカーのコーチを1年やって見えてきたもの
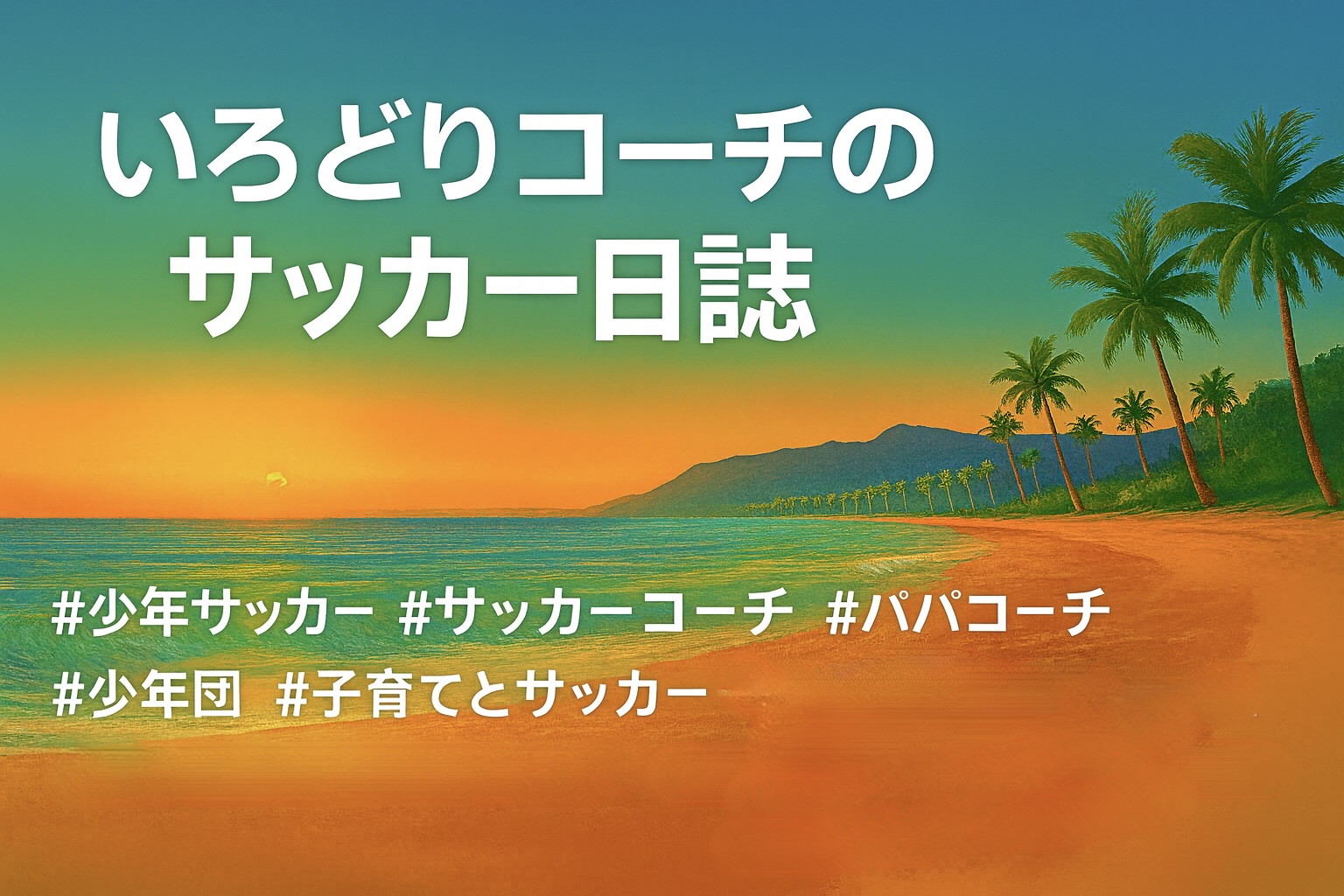


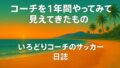
コメント